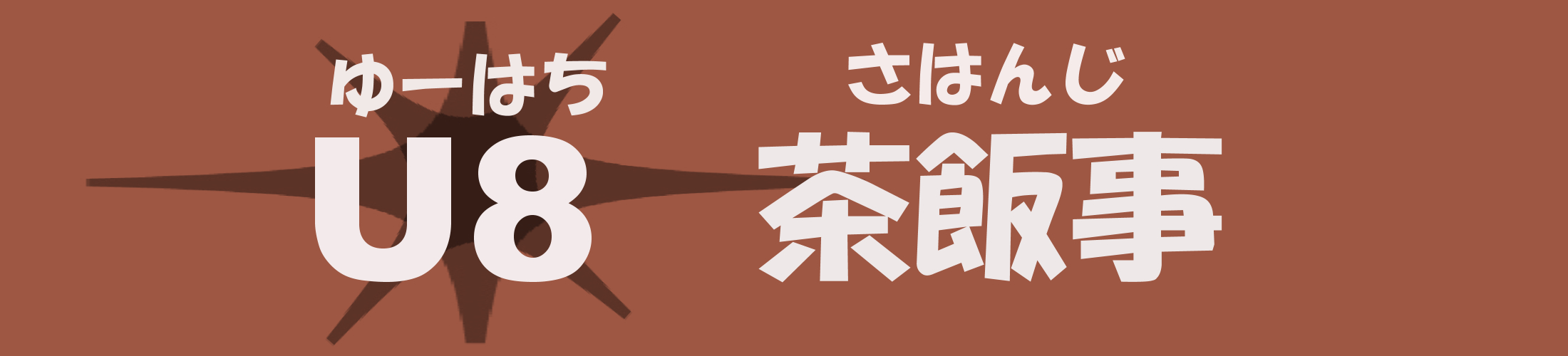話題の斎藤幸平さんの『人新生の「資本論」』を読んでみた。久しぶりに読むのに時間が掛かる大作を読んだように思う。ここで得た気付きや学びを使いこなせるように、何回かにわけて学びをアウトプットしてみる。
目次
人新世の「資本論」を読んで感じたこと
1.マルクスに固執し過ぎている
まずこの書籍で感じた印象はというと、マルクスにすごい固執しているということ。
世間一般で認知されているマルクスが出した『資本論』は、彼の晩成でさらに成熟させたものとはかけ離れていることの説明に半分くらい費やしている気がした。
何故そんなにもマルクスに拘るんだろう?経済学の世界に身を置いているとそれがベースになってしまうのかな?門外漢の私からするとそこまでマルクスの考えを打ち出さなくてもいいのにと思いました。
批判っぽいような印象を持った半面、彼がマルクスの晩成の研究から得た着想は面白くて、マルクスから切り離して説明したほうが一般受けするように思った。
2.ハイライト(学び)がとても多い
どこで見たか忘れたのだが、本の評判にハイライト※がかなり多い本であることが書かれていた。これに偽りはなく、私も285箇所もハイライトをしていた。
※ハイライトとはKindleで文章にマーカーの様に印をつける機能
私個人としては『資本主義から価値主義へ至る道』みたいな本を執筆しようと考えているのだが、この本の中で覚えた言葉を多用することになりそうだ。
人新世の「資本論」を読んで学んだこと
人新生の資本論ではいくつか言葉が定義されてる。新しいモノゴトを考え・説明する上では言葉の定義が重要で、少なくとも本書は40万冊以上は売れていて一定の浸透をしている為、定義された言葉を操れるように、振り返る。
人新生
人新生とは「人間たちの活動の痕跡が、地球の表面を覆いつくした年代」という意味で、ノーベル化学賞受賞者のパウル・クルッツエンさんが名付けたものです。
外部化社会
外部化社会は、都合の悪いことを外部に押し付ける社会のことで、資本主義で蔓延っている社会です。
例えると、きつい・汚い・危険みたいな3Kの労働を低賃金の国に押し付けたり、特定の資源を採取する為に他の資源を犠牲にしたりすることです。
資本主義は、営利を貪る為に都合が悪いことは外部化し、隠蔽し、先延ばしにするという特徴があります。これをする人ほどお金を儲けられる仕組みなのです。
ところが、資本主義の限界として現れたのが、上述の人新生です。人新生の時代には外部化が出来なくなり、成長が出来なくなってきているのです。
SDGsは現代版「大衆のアヘン」
昨今、SDGs(持続可能な開発目標)という言葉が叫ばれるようになったが、本書ではSDGsという言葉を語る事で、温暖化対策をしていると思い込み、真に必要とされているもっと大胆なアクションを起こさなくなってしまうことを指摘し、まるで現実の危機から目を背ける事を許す「免罪符」のように機能していると揶揄しています。
このことをマルクスが「宗教」を「大衆のアヘン」と批判したことに準えて、SDGsは現代版の「大衆のアヘン」と痛烈に皮肉っていましたが、的を得ていると感じました。
おわりに
今回の紹介だけで、この本を読みたいと思われる方はあまりいらっしゃらないかもしれませんが、気になった方は手に取ってみてください!
次回に続く
他にも学びがある書籍を色々と紹介しておりますので、気になった方は観ていってくださいね!
ご閲覧ありがとうございました。
ではでは(^^)/