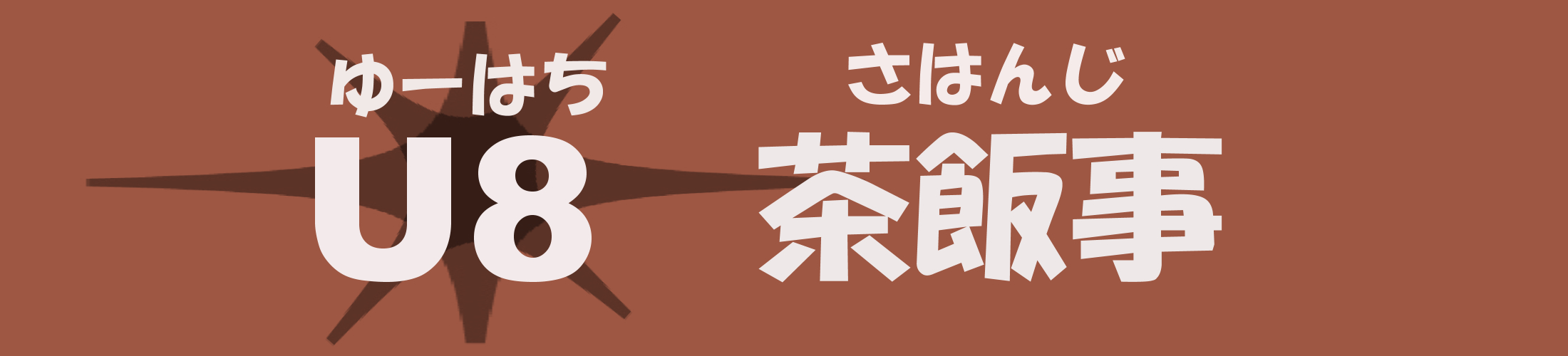大企業に長年勤めた社員の思考の固さはなんなの?ということで、昨今、仕事現場の同僚やSNSを通してお会いした一部の方に、年配者に観られるような思考の固さを持つ若者が居て、ヤバいなと感じる今日この頃です。
本稿ではこの原因が何で、どうやばくて、対策にはどうすれば良いかといった個人的な考察を共有します。
こんな方におすすめ
- 人生100年時代を楽しく活き抜きたい方
目次
世代間に観られるパラダイム
年配になるほど、新しいコトの話を受け付けなくなるのは、どの世代間でも見られるパラダイムです。多くの若者は年配者から考えを否定され、逆に「最近の若い者は」であったり、「俺の若い頃は」といった枕詞ではじまる説教にうんざりすることになります。しかし、このパラダイムは年配者が若者であった時に、彼らからみた年配者からも受けていたであろう状況と思います。
目上の方から、「最近の若い者は」を言われたなら、悲観せずに自分は正しいと考える位がちょうどよい。このパラダイムによる世代間の考え方や考えを支える視座の差が、時代を進展させる駆動力だからです。
同世代にも観られるようになったパラダイム
最近、「あれ?」って思うのが、この新しいコトの話をした際に、年配者ばりに話を受け付けない若者が増えてきていることです。これが私のリテラシーの低さや、凝り固まった視座によるものであれば、私自身の問題で完結するのですが、どうもそうではない状況です。
話をしていると、考えが深い話に行き着く前に、誰かに与えられたそれっぽい話での浅い理解に留まって完結してしまっている。
何がこの状況を育んでいるか、はっきりとした理解にまでは及びませんが、情報反乱による確証バイアスの強化であったり、情報検索対象が検索エンジンではなくインフルエンサーに移行しつつある状況が一因として働いている気がします。
前者の確証バイアスの罠については、別記事で紹介しているので気になったら観ていってください
後者は理解の理由を「インフルエンサー」に任せてしまっており「この人が言っているなら」といった浅い考えに留まってしまう点です。
若者が早々に年配者ばりの凝り固まった考えを持ってしまう理由
この思考の差が修正されれば良いのですが、どうもそういうアプローチが出来ていないように見えます。若くして、世代間ギャップのパラダイムにおける年配者ばりの防御で自分の考えを守ろうとする。
何故この防衛反応が働くのかというのは、世代間における年配者が、若い世代の考えを受け入れなくなる理由と同じで、次のような理由が働いていると思います。
- 努力して勉強して得たという自負
- 成功体験
- 安定環境での思考停止状況
では何故、この状況が早々に現れてしまうかというと、それは今の時代の流れが速すぎるからで、テクノロジーが指数関数的な進展をして、学ぶべきこと、多様な体験の場が創出されたことが原因と考えられます。
視座や思考を固定化することによるリスク
この状況下において、若くして自分の視座や思考を固定化してしまうことは、非常にリスキーです。何故かと言うと、この姿勢は若者が年配者が超克し続けてきた状況における若者側の立ち位置ではなく、超克される年配側の立ち位置である為です。
リープフロッグというテクノロジーの一足飛びに進展するという事象があります。この事象は、間のインフラやテクノロジーが整備されていないことが原因で発現するのですが、若者の思考回路にも当てはめる事が出来ると考えています。
つまり、間の知識や視座が無いが故に、年配者よりも新しい知識や視座を吸収出来るにも関わらず、それを避けて既に得た知識や視座に固執していまうと、加速する時代が矢次早に生み出す新しい知識や視座を吸収できなくなってしまう為です。それは、"オワコン"と言える状況に思われます。
視座や思考を新陳代謝するのに重要なこと
昨今の時代において、超克される年配側の立ち位置にならない為には、視座や考え新陳代謝していけることが必要であり、この為には、少なくとも次の2つの姿勢が必要だと考えています。
- 1つ目は新しい考えを受け入れるという姿勢。自分が知らないことがあるかもしれないという、「無知の無知」といったモノごとを視る謙虚な姿勢です。
- 2つ目は受け入れた新しい考えと古い考えを天秤に掛けて、どちらが正しいかを検分する姿勢です。検分の為に重要なのが、物事に対する深い理解であったり、成功体験の理由の正しい解釈です。この理解や解釈に掛ける努力を怠ると、物事を受け付けなくなる超克される立ち位置の人間になってしまいます。
おわりに
常識を新陳代謝するという、当ブログのコンセプトを体現する内容を書きなぐりました。途中に根拠の乏しい仮定や飛躍が大いにありますが、色々と自分が気づきとして感じたことを盛り込んだつもりなので、少しでもあなたに気づきを与えられていたら嬉しく思います。
他にも同様の考察を色々としておりますので、気になるタイトルがあれば観ていってください!
最後までご閲覧いただき、ありがとうございました。
ではでは(^^)/