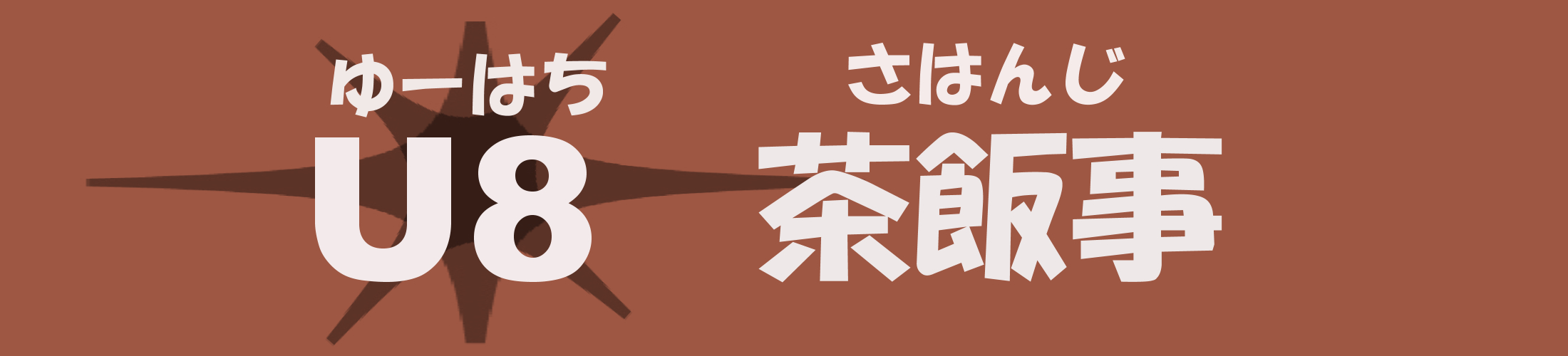おはこんばんにちは、ゆーはち@最近バイアスという言葉を多用するようになったバイアスって言ってみたいだけの人です。
今回は、一度突き詰めたコトを疑わない傾向を「探究済事項の盲信バイアス」と名付け、このバイアスを外した方が良いよってお話をします。
目次
「探究済事項の盲信バイアス」の危険性
現代人は探究済事項を疑いにくい
人は一度、何かを調べて結論付け、習得した学びがあると、その対象に疑問を持ったり再び学ぼうとしにくくなります。
これは一度苦労して学んだ、あるいは調べたという認知が、その人の意味記憶となり、考えを支える思考として定着してしまう為です。

この傾向は、「現状維持バイアス(status quo bias)」と呼ばれる考え方の癖に近いのですが、ピッタリくる解釈では無いので、冒頭でお話したように「探究済事項の盲信バイアス」と勝手に名前を付けてみました。
この「探究済事項の盲信バイアス」、昭和や平成の変化が緩やかな時代においては有効に働きました。しかし、現状のVUCAで進化が加速する時代においては、危険なバイアスです。一度突き詰めたことであっても直ぐに陳腐化してしまうからです。
現状維持バイアス(status quo bias)とは、変化や未知のものを避けて現状維持を望む心理作用のこと。 現状から未経験のものへの変化を「安定の損失」と認識し、現在の状況に固執してしまうこと。
引用:シマウマ用語集
探究済事項を疑わないと変化についていけなくなる
陳腐化して使えなくなった知識のままでいる危険性は説明するまでもないですが、時代の変化についていけなくなるからですね。
最近、既存と大幅に概念が変わったモノに2.0を付けて呼称するのが流行りました。この2.0の概念ですが、1.0に精通している人ほど正確に理解出来ません。
これは1.0と2.0で全く概念が異なるにも関わらず、探究済事項の概念で2.0を視ようとしてしまうからです。
例えるなら、サッカーのルールを野球のルールで当てはめて考えるようなアプローチをしてしまっているのです。
そして、そこで得た誤った認知でもって、誤った判断を積上げてしまい、落とし穴にはまってしまうのです。

バイアスってどれも、認知出来ていないと直せないもので、とりあえず「探究済事項の盲信バイアス」といった危険なバイアスがあるよってことを認知したいものです。
まとめ
今回は「探究済事項の盲信バイアス」という一度学んだ事を疑わないで、思考の前提にし続けるのは危ないよという話をしました。
我々が当たり前だと視て、思考の前提においている頑張って学んだ知識は、アスファルトのように盤石なものではなく、炎天下における薄氷のようなものと捉えるくらいがちょうど良いと思いますよ。
といったところで、今回はここまでです。
ご閲覧ありがとうございました。
ではでは(^^)/